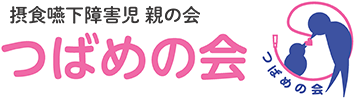第2回東海交流会はおしゃべりメイン
2018年11月24日(土)、第2回東海交流会を開催しました。
第1回は先生をお招きしての講演でしたが、今回は会員同士の交流を軸に、ゆっくり語り合える場としました。
参加したメンバーの声をお届けします。

子どもたちが遊ぶスペースを準備するスタッフ
会員の感想1
勉強会がメインだった前回と一変、今回は交流をメインに、心ゆくまでみんなで自己紹介をしました。
大変だった頃の思い出から現在進行中の悩み、果ては夫婦関係の問題まで、時間が許すかぎり話し尽くしました。
お昼には、京都から手伝いにきてくれた賛助会員が買ってきてくれた京都駅の駅弁を堪能。名古屋ではなかなか食べられない味に話もまた弾みました。
会場には子どもたちの遊び場も設置。高校生になった元経管栄養の子どもから、患児のきょうだい、まだ就園前の元経管栄養児たちまで、みんなで楽しく遊ぶことができました。
経管栄養の子どもたちは、経管栄養の間はもちろん、その後も大変なこともあるけれど、こうやって近くに一緒に頑張っている仲間がいるんだ、ということを再確認できた、素敵な時間でした。
―スタッフ M
会員の感想2
東海交流会、スタッフ兼患者家族で参加させていただきました。
今回は、前回と違い交流の場ということで、みなさんの話を聞き、日頃なかなか他人に話さない我が家のチューブ事情などの話をさせていただきました。
街角で出会った方に「お子様何歳ですか?」と聞かれた時の話は、相手は悪気はないのでしょうけど、実際の年齢を答えても理解してもらえないから、あやふやに答えたりすることは、私もあるある、と思いながら聞いておりました。
物を食べない、食べにくい子供を知っている方でないと話していても中々理解が得られず、普段から話すことをしてなかったので、個人的には新鮮な気持ちでした。もちろん医療関係、リハビリ関係の方には相談を含めて話はしておりますが、当事者間での会話はまた違い、気持ちが楽になりました。
メーリスで日本全国の方と繋がれる環境ですが、やはり顔を合わせて話すのが良いなと感じました。
勿論、外出をするのが大変だったり、周りの目が気になるという方もいらっしゃるかもしれません。たしかに大変です。注入の管理、準備品、バギーなどはバリアフリーあるか確認するなど、様々な日常とは違う手間が増えるかと思います。
それでも新たな発見があるかもしれませんし、まわりにチューブっ子がいて、食べられる子、飲むことはできる子もいる中で、子供自身も色々な場面や食べる風景をみたら、何かが変わるかもしれません。
今後も、東海、関西限らず全国色々な場所で交流の場が出来ればよいですね。微力ながら、お手伝いできればと思います。
―患者家族・スタッフ A