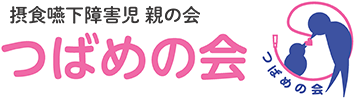子どもの食べる機能の発達について、親にとってわかりやすく紹介されている説明や文章はあまりありません。
それどころか、さまざまな理由で食べない子供を持つ親が専門家にかかりたいと思ったときに、歯科という選択肢があがることもあまりないのではないでしょうか。
そもそも健康で問題なく食べる子を持つご家庭であれば、食べられない子供が歯科で診察してもらうことを知っている方はおそらくかなり少ない割合なのだと思います。つまり親が食べない子供のための歯科受診を何もないところからイメージするのは難しいのが現状です。
もちろん医師にもそれぞれの専門科があるように、歯科なら全てこの問題のエキスパートというわけではないのですが。
さて、このような中で、つばめの会の顧問に加わっていただいている歯科医師の綾野理加先生が
子供の食べる機能の発達や食べられないお子さんについて、
親御さん向けにまとめてくださっているのでご紹介します。
noteで連載されており、今後も記事が追加されていくそうです。
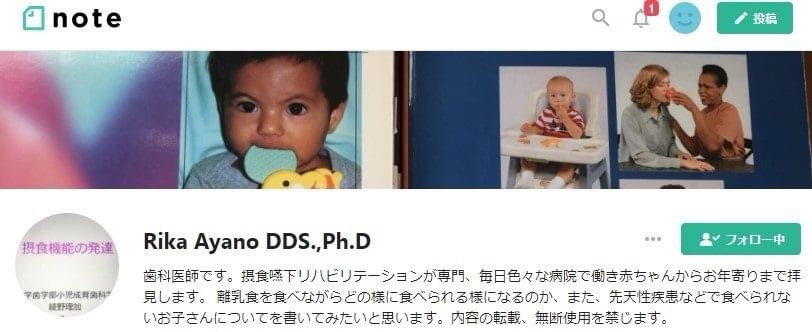
本日までに掲載されている各記事のタイトルはこのようになっています。
食べる機能の発達❶はじめに
食べる機能の発達❷離乳初期
食べる機能の発達❸離乳中期
食べる機能の発達❹離乳後期
食べる機能の発達❺手づかみ食べ
食べる機能の発達❻母乳や哺乳びんでの飲み方とスプーンやコップ、ストローでの水分の飲み方の違いについて
食べる機能の発達❼スプーン食べについて
例えば❶はじめに にはこのような文章があります。
““” 離乳食について親御さんが学ぶ機会は離乳食講座や離乳食の本、ネットの情報のように思います。この時期にこのような形状の食事を与えましょう、という情報は多くても、その形状の食事を食べながらどうやって食べる動き(食べる機能)を身につけるのか、という情報はなかなか保護者の方の元へ届いていないように感じています。
ここで書いていく、食べる機能の発達、が、離乳食の進め方やお子さんの食事のヒントになったら、と思っています。 ””
これは知りたい!という方が多いのではないでしょうか?
食べる機能が専門ではない医療・福祉の方々にもご参考になるかと思います。
つばめの会でも連載をとても楽しみにしています。