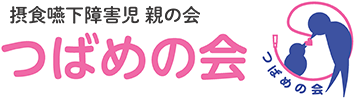本日はグラクソ・スミスクライン株式会社が患者団体向けの勉強会として開催されている「J-PALSアカデミー」オンライン勉強会に参加しました。
勉強会テーマは「オンラインイベント」で、
株式会社ミミクリデザイン ディレクター田幡 祐斤さんによる以下のタイトルのオンラインでのセミナーでした。
「参加者にとって居心地の良いオンラインイベントとは?
~オンラインイベントのプログラム作りや進め方のヒントを学ぼう~」
いまや大勢の方がオンライン会議を使うようになっています。
つばめの会は3年前の講演会を中継した時からzoomを活用してはいましたが、完全にうまく行っていると言い難いこともあります。
そこで今回、つばめの会から3名が参加させていただき、とても勉強になりましたので以下に感想をご報告します。
オンラインのちょっとしたトラブルや対面でのコミュニケーションに劣る部分は誰もがいくつも思い浮かぶと思うのですが、それはオンラインを対面コミュニケーションの代替と考えるからだという視点が非常に新鮮でした。
たとえば長電話は心地良いコミュニケーションとなることも多いと思います。オンラインは対面と違い、長電話のようなそれぞれ別の場所で別のことをしているからこそ、対面では出ない話が出来るコミュニケーション方法である、と考えることができる、という、対面にはない利点のお話が印象に残りました。
たとえばオンライン会議で、子供の世話をしているからオンラインで会議を「聞くだけ」の参加、または、声を出すと子供が起きてしまうからオンライン会議で「チャットだけ」の発言、など多様な参加が可能になる、というのも利点と考えられます。
会話のタイムラグが発生しないように、すべてのトラブルが、起きないように、という考えではなく、トラブル起きる前提で、主催者が話をして参加者の協力意識を作ることで、トラブルを対面と比べたマイナスなだけのものにせず、オンラインならではの利点を活かす考え方も参考になりました。
さらに印象深いのは、「たとえばチャットの入力が苦手な人やオンラインが苦手な人によくないコミュニケーションなのでは」という考え方に対して
「対面のコミュニケーションは、万人にとって有利なツールではなかったのではないか、対面コミュニケーションが苦手な人もいたのではないか」という視点はとても重要であると思います。
一つ前のブログ記事に続いて、オンラインをやりとりのツールに加えることはまさにdiversityと言えるかもしれません。
つばめの会は、発足当時から外出もままならず近所の方とコミュニケーションを取る時間も取れない経管栄養児の子育中でもやりとりができるように、メーリングリストの交流がメインです。
したがって「対面サポート」が多い患者会と比較すると既にオンライン活動に近しいといえます。
しかしそれは対面の代わりと考えていたので、対面にないオンライン会議を活用する方法や視点があるという視点は、非常に新鮮でした。
さっそく参加した3名でセミナー後に別途オンライン会議を行い、本日のセミナーの具体的な活かし方を話し合いました。
たとえば教わった「噂話トーク」はオンラインを利用して将来的にはオープンダイアローグのリフレクティングという手法のように会員同士の交流をすることに活用できるのではないか、これで参加者の悩みに対しての俯瞰や自己理解につながるようなアプローチができるのでは、というアイデアが広がりました。
実際にスタッフ同士でのチャレンジから始めてみようなど具体的な案が出され、さっそく学んだ「噂話トーク」をスタッフ会議で実行してみようと計画しています。

講師の田端先生、またこのような企画を実行してくださったグラクソ・スミスクラインのみなさまに感謝申し上げます。